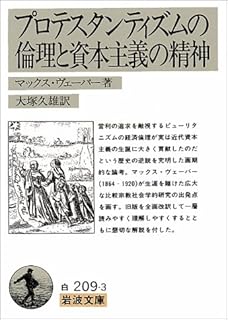この前に書いたブログ『ヘンリー8世の人生を描いた人気ドラマ「THE TUDORS〜背徳の王冠〜」』で、ヘンリー8世が、政治基盤の脆弱性を補うために男子(王子)誕生をのぞみ、その結果としてイングランド国教会を、ローマ・カトリック教会から分離・設立したことを書きました。
今回は、その後の産業革命へと続く道筋において、エリザベス1世の果たした役割について書いてみようと思います。
 |
| エリザベス1世 |
そのためには、エリザベス1世が、父・ヘンリー8世が行った政治的な宗教改革を、彼女はどのように受け止めていたのか、を知る必要があります。
嫡出か?庶子か?それがエリザベス1世最大の問題
エリザベス1世は、ヘンリー8世によって母・アン・ブーリンが処刑されるとともに庶子の身分に落とされてしまいます。ヘンリー8世にとっては、メアリーに続く存命する2人目の嫡出子であり、誕生と同時にイングランド王位推定相続人となったにもかかわらず、です。
姉のメアリーも、母のキャサリン・オブ・アラゴンが離婚されたときに庶子の身分に落とされ、そのうえエリザベスの侍女のような待遇になっていたと伝わっています。
エリザベス1世は、プロテスタントおよびカトリックの法に基づけば、厳密には庶子でありましたが、イングランド国教会においては、非嫡出子であることを取りざたされる可能性は低かったと考えられます。
そのためエリザベスは、姉・メアリー1世がプロテスタントを排斥したことを踏まえ、現実的な宗教政策を取り入れています。
それが、イングランド国教を宗教的に整備することでした。
ヘンリー8世が定めた国王至上法(Act of Supremacy)は、イングランド国王を「イングランド国教会の地上における唯一最高の首長」と宣言するものです。
イングランドにおける宗教改革の重要な契機であり、政治的性格の強いものであったため、国教会の正統性や教義内容については、エドワード6世、メアリー1世、エリザベス1世の時代に至るまで問題とされていました。
ローマ・カトリック教会から分離・独立したとはいえ、カトリックとの違いは、首長が教皇なのかイングランド王なのか、なのかしかなかったのですから、仕方がありません。
エリザベス1世が法制化した、新たな国王至上法では、全ての役人は最高統治者たる国王へ忠誠の誓約が求められ、さもなくば役人の資格を剥奪されることになります。
同時に、礼拝統一法 (Act of Uniformity) が可決され、週に1回の国教会礼拝への参加と、1552年版聖公会祈祷書(Book of Common Prayer)の使用を必須のものとしましたが、国教忌避または不参加、不使用への罰則は厳しいものではありませんでした。
ローマ・カトリック信者がまだ多いと推測される時代ですから、エリザベスがイングランド国教会の法的整備を進める一方で、カトリック信者への寛容さを見せているのも、現実的な選択であったのでしょう。
英国国教会へのカルヴァン主義の導入
ヘンリー8世の宗教改革を推進したトマス・クランマーは、カルヴァン主義の影響を受けていたため、1548に完成した最初の聖公会祈祷書には、カルヴァン主義的色彩が導入されたものと推測されます。その後、スコットランド人で長老派(カルヴァン派のスコットランドでの呼び名、プレスビテリアン)教会の創立者でもあるジョン・ノックスが、歴史の渦に巻き込まれて1549年にイングランドに追放されます。
このときの王はエドワード6世。
彼の王室付属牧師となったジョン・ノックスは、ここで聖公会祈祷書の作成に影響を与えます。
ここで、イングランド国教会にカルヴィニズムが導入されたことは、のちの経済発展に大きな影響を与えます。
20世紀初頭、ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーは「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」と題する論文で、カルヴィニズムの影響が強い国では、近代資本主義が発達した一方、イタリアやスペインなどのように、カトリックの影響が強く、実践的合理性の顕著な国やドイツなどでは、資本主義の発達が遅れたことを明らかにしています。
| プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 (岩波文庫) | ||||
|
まとめると、ヘンリー8世がローマ・カトリック教会から政治的に分離・独立し、のちにエリザベス1世がイングランド国教会に関して法制度化したことにより、カルヴィニズムがイギリスに定着し、産業革命に代表される経済的な発展を遂げることができたと言えます。
日本人には想像できないかもしれませんが、このころすでに宗教改革がはじまっていたとはいえ、ローマ教皇の権力は絶大でした。
当時のヨーロッパ人は、ローマ教皇と封建領主の双方に支配されており、序列としてはローマ教皇のほうが上だったのです。
しかし、マルティン・ルターや思想家ジャン・カルヴァンによる宗教改革が進行する程度にはローマ教皇の権力にほころびが見えてきた時代でもありました。
ローマからみたら辺境といってもよいイングランド王が、イングランド国教会を分離・独立できたのは、ローマから遠く離れ、しかも海を越えた島国というイングランドの立地が大きく影響したことは間違いないでしょう。
しかし、教皇権力が弱まってきたこととも無関係ではないのです。
宗教的影響を受けない「未婚の女王」という選択
エリザベス1世が、未婚の女王だということは有名な話です。これにも、結婚によって宗教的な影響を受けないという外交上の理由があったとする説が有力です。
当時の大国は、スペインや神聖ローマ帝国(現在のドイツ)であり、これらはカトリックの国々でした。
ヘンリー8世の最初の妻がスペイン王家出身であったように、イングランドにしてみれば、まだまだ国力の弱い国家を支えてくれるような後ろ盾が欲しいところであったと考えられます。
しかも、ローマ教皇の力はもう頼れません。
このような環境のなか、結婚を外交上有利にするためにつかったとされる、エリザベス1世の処世術。
結婚によって、夫の国からの介入を受けることは絶対に避けること。
これがエリザベス1世の考えであり、基盤の安定していないイングランド国教会への配慮であったと考えても良いのではないでしょうか。
| 女王とプリンセスの英国王室史 (ベスト新書) | ||||
|
<関連の投稿>
ヘンリー8世の人生を描いた人気ドラマ「THE TUDORS〜背徳の王冠〜」
映画「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙」